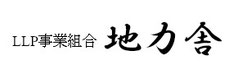Si22,Si25を使ったかんたん稲作
育苗
- モミの塩水選後、脱塩浸水の終わりにSi22、2000倍液に24時間浸漬した後、風乾する。
- 苗箱に従来の半分程度に薄撒きして発芽させる。
- 発芽後、育苗ハウスは風が抜けるようにして、数日おきにSi22、2000倍液を散布する。
- 時々苗にローラーをかけ、いじめるほうがより好ましい。
- 田植え前に、苗の根絡み処理を必ず行う。
根張りのよい、勝手に元気よく育つ苗を作ります。
田起こし前にSi25、6kg(2袋)/10aを散布して、やや深めに攪拌します。永年化成肥料を使用してきた田園は、不溶化している肥料を可溶化するために初回だけ9~12kgが望ましい。

基肥と茎肥
- 化成肥料の場合は、原則基肥なし。有機肥料や堆肥の場合は、地力に合わせてチッソで4~6kg/10a程度を施す。
- 化成肥料の場合7月1日ごろ、化成一発肥料を茎肥としてチッソで4~6kg/10a投与。
根を張らせ、ゆっくり分げつと節間がつまったしっかり茎を作ります。
田植え
- 粗植が望ましい。6条植えでは養分と光の奪い合いをして、徒長ひょろ茎気味になり下葉が垂れる。そのために稲間が高温多湿になり、病害虫が出やすくなる。
- 雑草が気になるときは深水で、スクミリンゴカイが気になるときは貝殻が水面に出る浅水で2~3週間管理する。
- 分けつ期までは葉色は薄い。この時あせって追肥をしないことが大切。

7~8月
- 施肥量を抑えているので、中干しは原則不要。
- 高温、冷害傾向が見えたら、Si22、2000倍液を葉面散布すると±3℃程度抵抗性を増す。
- ウンカ、いもち病の気配を感じたら、同様の処理をすると抵抗性を増す。
- 穂肥は原則やらない。
- 出穂期から葉色、止め葉長、止め葉幅、ケイ化が増加し、一段と好ましい姿になる。
- 実肥えは出穂10日後ごろ、Mg>K>Nを適量施肥。(過多は食味低下を招きます。)

9~10月
- 落水はじめ
- 葉色がますます鮮やかになります。光合成が盛んになり、登熟を促進を促進します。
- 葉は黄化しにくくなるので、モミの登熟具合を確認して刈取り時期を決めてください。
- 刈取り

11~12月
- 稲わらは燃やさずに敷き置く。
- 12月初旬にSi22、2000倍液を田園に散布する。(稲わらと残根の発酵分解と翌春の微生物の増殖促進のため)
要点
- 気候条件に恵まれると、枝こうあたりの粒数が10%~20%増える。V字枝こうが発生し、枝こう数も10~20%増える。
- 良作の証としてノゲが出ることが多い。
- 翌年の施肥量はより少なめが好ましいと思われますが、流入する河川の栄養分や品種特性(多肥多収型)にもよるので、EC測定等のうえ総合的に判断してください。
- 分げつ期中頃までは養分が地下部に傾くために、地上部の成長に不安を感じることがありますが、根を確認して大きさ、一次根と二次根のバランス、白根であればそのままで心配ありません。