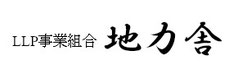一部 名人の話に学ぶ
イチゴ生産者さんの半数以上はJAさんのイチゴ部会で出荷していると思いますが、つい周りが気になりますね。収穫期は他所を見る余裕はありませんが、作の終わりには成績が総収量、反収、販売額などいろんな形で発表され、優秀者は表彰されたり、会報に載ったり、栽培講習の指導者に任命されたりと誇りがくすぐられます。
収量×単価=収入額とみて、これまでは生産量の増加を一番の目標として、作付け面積の拡大や反当り作付け株数の増加が指導されてきました。その成功例のように「イチゴ御殿を建てた」「反収8トン採り」などのニュースも多く報じられていますが、今あなたは何トン、いや何パック採れていますか?
パック数のカウントは正確な成績に近いと考えますが、何トン採りのデータや話は思惑や自慢の気配が感じられて余り信じられません。1パック=300gとして3パックでほぼ1kgとすると、4トン採りで12,000パックになります。集荷パック数をオンラインで生産者管理しているある先端県でも平均は4トンにわずか届いていないのが実情です。
イチゴは反当りの販売額が一番の作物であることは確かですが、その分生産にも調整にも手もコストもかかります。量を追う、つまり自分の能力を超えて、作付け数を増やし肥料に頼る栽培になるとどうしても一株あたりの手のかけ方は減ります。さらに肥料が多いと作物は軟弱に、病害虫は寄り付きやすくなります。収獲期間だけでも6カ月余という長丁場はご自分とイチゴの健康を損なわないちょうど良い収穫を心がけることが、結局お金が残ることになります。
私たちが成長して生きていくために不可欠なものは空気(酸素)、水、食べ物(有機物)です。植物にも空気と水は必須ですが、食べ物つまり栄養は無機物でかまいません。また空気を構成する分子の中でも酸素よりも炭酸ガス(CO2)が植物にはより重要です。私たちが食事をし呼吸をしてエネルギーを得る仕組みを化学式になおすと
C6H12O6(グルコース)+6O2 → 6CO2+6H2O+エネルギー
になります。ちなみに車のエンジンでガソリンを燃やすのは
C5H12(ガソリン)+8O2 → 5CO2+6H2O+エネルギー
で、エネルギーを得て炭酸ガスと水を排出するところはよく似ています。では植物が光合成をして有機物(グルコース)を作る仕組みの化学式は
6CO2+6H2O+エネルギー→C6H12O6(グルコース)+6O2で、
最初の式の反対になり植物が有機物と酸素を作ってくれていることが解ります。このときのエネルギーは太陽のエネルギーで、お天道さんが照らないと光合成が始まらないことが理解できます。葉でグルコース(糖)が出来ると葉、茎、根、花、果実などの増殖部位へ転流させて、根で吸収したN,P,K他の無機物と反応させて細胞を構成するたんぱく質や脂質や核酸をつくり、細胞分裂のための材料を揃えます。光合成の始まりにはお天道さんとCO2と水が必要なことから、近年は炭酸ガスを発生させる機械を「光合成促進機」と称して発売されていますが、CO2削減が地球環境的に叫ばれている昨今やや異に感じないこともありません。人がCO2を供給することより植物にCO2を吸う力を持たせることが大事ではないでしょうか。このことは肥料でも同じです。
30歳で栽培を任されて70歳まで続けたとして40年。同じ年は1年も無いはずです。従って毎年1年生の気持ちで勉強しなければという謙虚な姿勢の現れです。天気で言えば日照、温度、湿度、降水量が違い、種苗の出来も病害虫の発生も毎年違います。農業は条件の設定が膨大複雑で「こうすればこうなる」という法則のようなものは無いに等しく当てには出来ませんが、現状分析をしてなぜそうなったかを探ることがご自分の栽培技術の引き出しを増やすことになります。そしてそのことを栽培記録として残すことも大事で、積み重ねれば間違いなくあなたの財産になります。名人たちは難しい問題に出会ったとき「困った・・・」という言葉と裏腹に「どう、片付けようか・・」と手ぐすね引いているような感があります。問題をやりがいに変えるような引き出しを揃えたいものです。
イチゴ栽培は果実を採ることが目的ですから、良い玉を採るには良い樹でなければなりません。良い樹は良い根の上に育ちます。良い根は良い土に育まれます。良い土は肥料を使わなくても良い果実が適量実る土です。土壌分析も時系列で捉えることで化学的組成や腐食のバランスを知ることができますが、最も大事な微生物の菌叢までは解りません。あなたのハウスの土では長い歴史を乗り越えてきた「土着菌」が主役です。栽培にとって良いのも悪いのもいますが、そこにいる以上私らには解らない環境維持に何らかの役に立っているのでしょう。悪いといわれている菌や害虫は体チッソ率が押しなべて高く、入れすぎた肥料は彼らを繁殖させて被害を増大させる結果になります。そうなると消毒殺菌の出番ですが、どんな消毒も良い菌と悪い菌を選んで殺すわけもなく、また100%絶滅させることもハウスでは不可能です。数パーセントでも生き残れば、窒素過剰の圃場では悪い菌から数日のうちに増殖し、元の木阿弥になる危険性も否定できません。良い土の判断はミミズの密度でみるようにしています。ミミズは良い菌と共生し、どちらも塩分とアンモニアが苦手ですから、ミミズが見られない土は肥料過剰と判断できます。現在の先進国や発展途上国の農地の大半は肥料過剰、ケイ酸不足で、ミミズとも出会うことが少ないと言われています。またミミズの活動が膨潤な土壌を作ること、ミミズの糞はまだ人間が作り得ない最上の肥料であることに研究者は称賛を惜しみません。近年、有用微生物の活用が注目され始めていますが、あなたの圃場の「土着菌」との相性を念頭に置くことは大事です。
肥料を入れないとイチゴの量は採れないという感覚に縛られていませんか?あるいはミミズがいない、循環性の弱い地力のない土の場合は施肥に頼ることも致し方ないかも知れませんが、肥料頼みは長続きは見込めません。イチゴが育てば土には根酸や微生物酸が貯まり、根に吸収されたカリ、マグ、カルシウムは地上部へ移動して酸性に傾きます。葉は余分なカリ、マグなどのアルカリ分は葉水として排出しますが、ハウス内では雨に打たれることがなく、マルチで土と隔離されるので土に戻ることはありません。ハウスの土の酸性化は宿命で、pH5を下回るとイチゴ生育の不調が現れやすくなります。多いチッソの投与は土の酸性化をいっそう促進させることを心に留め置きましょう。イチゴの状態が思わしくないときは、大半根が緩んでいるはずです。または根が緩んだあとには不調が現れやすくなります。水不足でなければ、強めの葉欠きと摘果をしてやれば、早々に元気を取り戻すはずです。頭でっかちは肥料過多と親戚みたいなものです。
「苗半作」から八作に変わりつつあります。気候変動で育苗期の高温が苗作りを一段と難しくしています。太陽は光合成に不可欠ですが、イチゴはどちらかというと寒いところの原産で暑さはあまり得意ではありません。まして苗の時は人間でも赤ちゃんから小学生にあたり、病気や事故が心配な時期です。作業性の効率から山上げをやめてハウス脇での育苗、経済性から早出しのための人工低温処理とイチゴ苗にとって温度、水、病害虫など取り巻く環境は厳しくなるばかりです。育苗の目標は①必要な苗数を作る②病害虫被害を最小限に③クラウンのしっかりした良苗づくりがあげられますが、名人たちはイ、暑さで老化気味の太郎苗は予備苗として苗数に入れない ロ、定期防除よりも発見即防除で農薬耐性を避ける ハ、十二分な葉欠きと後処理を心掛けることをされています。自分で生き抜く力を備えた苗は、厳しい環境や条件にも簡単には負けません。
ある名人がバス3台で来た研修者を前にご自分のノウハウを惜しげなく伝えていました。「将来ライバルになるかも知れないのに大丈夫?」との問いに
「帰ってやってみるのは大していない。またこことは違うからその通りにはいかない」つまり、研修は参考になっても答えにはならないということです。私の訪問の折、名人の多くは時間があったら見て行ってくれと、試験区に案内することが少なくありません。第三者の評価を聞き、独善にならないためでしょう。「いい話を聞いた」「いい資料が手に入った」ら名人は自分のところで再現を試みます。「やってみないと解らない、覚えない」そうです。ご自分のハウスでご自分のいちご作りの一番の名人となるのは、あなたの他ないはずです。
一般的な植物もイチゴも90%以上水で出来ていますが、意外と水のやり方が足りていないことがあります。肥料と違い水にはなんの栄養素も無いとか、やり過ぎると水っぽくなるとか根腐れになりやすいなどの理由があげられますが、細胞の機能は全て水を介したものであり、水の不足は機能の不全が避けられません。葉や茎の地上部には水の浸透を防ぐ機能や、過剰になった水を排出する仕組みが備わっていますが、地下部の根のそれは非常に弱いものしか無く、過剰の害は根に出やすいのですが、同時に土の排水性の問題でもあります。イチゴは水過剰も肥料過剰も嫌がりますが、水不足は一番の苦手です。
JAさん出荷の方々をみると集荷時間から逆算してパック詰め、収穫が行われているように思います。収獲時に病気や害虫を見つけても、防除処理は集荷から戻ってからとなってはいませんか?このことが改善すべき一番のポイントです。病害虫は世代交代、増殖のスピードが私たちの感覚より何倍も何十倍も早いので、拡散はあっというまです。拡がった病害虫の退治はクスリが効きづらい昨今至難な業になります。病害虫を見つけたら、その場で即、対応することが肝心で、Si22の1000倍液や常用薬を身近に備えておきましょう。平均的な収量でも病害虫が員数のうちに押えれば、それなりの収益は見込めます。出荷を一日休んでも、病害虫の初期対応のほうが大切です。
路地のイチゴは前年の秋に花芽分化をして、冬を休眠状態でやり過ごし、地温と気温の上昇を感じて3月ごろ花を咲かせ、5月中ごろに果実をならせる通常一度きりの開花結実です。イチゴの生理を利用したハウス栽培は、人工的な春の環境のもとで数回の収穫を可能にして商業作物としての価値を確立しています。品種や腕前によっては7番果取りや9トン取りの情報も聞きますが、毎回見事な栽培や収穫を続けている方は知りません。イチゴが花をつけて実をならすのは年一回の大仕事で、大なりの100点を望めばどうしても樹に疲れが出ますが、摘果(花)、葉欠き、芽欠きの手入れをすることで軽減できます。根への負担が大きかった場合は次の花の上がりが著しく遅れて、内葉ばかりが増えて果実の収穫は期待出来ません。従って上手な方は肥料の出し入れと手入れの強弱で、価格が良い取る時期と価格が下がった休ませる時期を組み合わせます。盛期で手入れも適わないときは、次の根を促すためのSi22の密な潅注はテクニックにひとつになっています。
どんな名人達も最初は新人です。多くの失敗と苦境を乗り越えて今があります。経験の無い難題にぶつかったとき、大半の名人が口にする言葉が
「現場をよく見る」
すると
「イチゴが教えてくれる」
そうです。イチゴに教えられたことが多いほど、良い生産者への道を歩んでいるはずです。