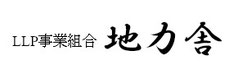二部 いちご栽培チェックポイント
お天道さん、水、温度、湿度、肥料の過多、過小の順にデータをもとに確認しましょう。
お天道さん(日照)・・・・50%~
水(土の水分率)・・・・・≒30%
温度・・・・・・・・・・・15℃~25℃
湿度・・・・・・・・・・・50%±15%
肥料・・・・・・・・・・・基肥EC 0.3 生育期EC 0.1~0.2
以上の目安から相当外れると、生育不良、病害虫の発生の可能性が高まります。お天道さんはどうしようもありません。水、温度、湿度、は工夫次第で改善できます。肥料が多過ぎるのはイチゴが吸ってバランスが整うのを待つしかありませんが、その間の出来栄えは期待薄です。足りない時は薄い化成肥料をやれば一両日で改善するはずです。

やり方仕方はそれぞれですが、苗数確保、病害虫最小化、葉欠き励行が最重要。苗質、ポット泥質、水遣り、温度日照調整、適正施肥をチェック。週1枚新葉展開があれば正常。病害虫が出やすい時期なので抜かりない観察とすばやい対応が大事です。発見前の定期防除はクスリの耐性をつける恐れがありお奨めしません。先年炭ソ病の流行から葉欠きを推奨しない指導が増えたようですが、放っていても自分で生きていく強い株に育つ苗は葉欠きが作ります。葉を3~4枚残しで週に1枚づつ5~6枚欠いでやれば、定植時にクラウン径10~12mmの優秀な苗に育ちます。クラウンに残る葉欠き跡からは花芽ごとの不定根が出やすくなるので、地上部/地下部(T/R率)が整ったなり疲れの少ない株が期待できます。
さし苗の場合は早めの切離しですが、つけ苗では親株と子苗ランナーが繋がっていることで育苗前半の栄養は親から子へ、後半は子から親への流れが勝るようになります。前半は親だけを管理すれば親が子をみるこで省力化されますが、後半は弱った親が足を引っ張るようになると子の成育にも弊害が出ます。病気の発生は疲れた親からのことが多く、立枯れ病などは繋がっていれば親子一斉処分ができますが、切離し後では親子の素性が不明になり、本圃に保菌株を定植する危険性がぬぐえません。ベストな切離しのタイミングは経験で測るしかないかも知れませんが、個人的にはお盆前後が適当かと思います。親株からの伝染病予防として、苗数が揃った6月頃の早い切離しの指導も見受けられますが、東北農試の研究によるとその時期ではもう先端苗以外伝染済みであり、さらに苗だけの栄養吸収では足りずに成長不良になる不安も残ります。さし苗は伝染病リスク承知で、省力化優先の育苗ですが、出来るだけクスリに頼らず病害虫を最小限に抑えることが求められ、Si22の週2の散布が助けになると思います。

早出し策として短日夜冷処理や低温暗黒処理などがありますが、当然コストもかかりご自分のところの規模、労力にあった範囲で普通株との比率を決めるべきです。ただ早出しはイチゴの生理にはマイナス要因が多いとみますので、余り多くを対象にすることはお奨めできません。近年お盆後の高温が続く環境下では、苗の冷え方不足で腋花房の展開が減り、一番果の減収の一因にもなっているので、定植前に普通株を2~3日冷蔵することも有効のようです。

毎年か少なくとも隔年の土壌分析の実施が望まれます。ファイリングしておけば土の化学性の変化が見えてきます。足りないものは足し、多いものは入れないが原則ですが、「やや少なめ」の範囲を「腹八分」とするほうがちょうど良いかも知れません。腐植は保肥力を高めますが、入れ過ぎるとフザリウム系の病害が出やすくなります。腐植の保肥力は永続性に欠けるのでケイ酸(Si25)で補いましょう。土壌に一番大事なのはイチゴと共生する微生物の存在ですが、これは土壌分析では見えにくく、ミミズの密度が多ければ大丈夫とみていいでしょう。
土壌チェックに基づいて手当してください。ECが0.3あれば基肥不要、それ以下の時の肥料はチッソ3kgを越えないように。「大は少を兼ねる」や「とんでも素晴らしい資材」の話を試してみるならごく一部の圃場で、実施施肥量の記録もお忘れなく。
土耕栽培なら斜め浅植えが根張りが良くなるのでお奨めです。より大事なのはクラウンについた泥を洗い流すことと、畝高に迫る水遣り。地下に沈んでいくこの水を根に追わせ、初期根を充実させるために後の水遣りは1週ほど控えます。ただ毎朝新葉に葉水がついていれば良し、無いときは夜伸びる根が地下の水に追いついていないので、水をやってください。根の活着までは毎朝の水遣りが指導されるようですが、経験からは浅根になって温度変化に左右されやすい株に育つように思います。高設栽培は密植になることが多いようですが、株間にゆとりを取ることは好結果を生むことが少なくないので、一度はひとつのベッドでもお試しを。
気温が17℃になるころマルチを掛けますが、しばらくは肩止めにして地温が上がり過ぎないようにします。スソ下しは10月下旬ごろですが、寒暖次第で判断します。穴あきの白黒マルチの先張りは地温上昇傾向が強いためノキ勝ちになりやすいので、マルチの肩止めとスソ下しには特に気配りを。
スソ下しと大体同時期です。17℃以下が続くようになったら行いますが、共同作業の場合は自分の都合ばかりを言っておられません。要はハウス温度と地温がこの時期は上がり過ぎて樹がボケないように。
気温が13℃を超えなくなったころサイドを閉めますが、お天気の昼間のハウスは高温になるので、20℃辺りを目安に開閉してください。この頃早い寒波の到来もあり、余りの寒さには合わせないほうが賢明と思いますが、「一度は当てたほうが樹がしっかりする」と言う名人もいて、品種によるのかなとも思います。
ハウス温度が5℃程度になったら出番ですが、その前に必ず試験焚きをしましょう。いざとなって点火しなかった、夜中に消えてしまったなどで、出だしでつまづいた例を知っています。指導は6~7℃でのセットですが、名人では2~3℃の方も数多いようです。重油コストと栽培法との兼ね合いですが、ボイラー使用は①ハウス内に霜が降りて花をダメにしない②花が八部咲きになったら、昼間ハチが働く15℃にする・・・ことが矮化防止よりも大事です。矮化は地温が13℃以下の日が続かなければ、起きることは少ないはずです。
電照のエネルギー量は日照と比べようもなく成長促進は期待できませんが、日長保持の意味で休眠を抑制する効果は認められます。ただ過ぎるとノキ勝ち傾向の草体になりやすく、二番花の停滞も否定できません。イチゴの電照に対する反応も品種差が大きく、品種特性を知った上で適切な管理が望まれます。二番花の開花の重要性が問われる昨今、電照不要の新品種が増えていることからも以前ほどの重要視は無くなりつつあります。代わってUV-Bという紫外線ランプでウドンコ病予防が提案されているようですが、効果対費用でみるとSi22を使いこなすほうが収益には有効と思われます。
電照と同じく以前ほどの重要視は無くなりつつあります。もともと体内で作られる内生ジベレリンが諸条件で生成が遅れたり、足らなくて成長停滞が見られる場合に使われましたが、むしろ出蕾時に果梗枝を伸ばして玉の着色を良好にするための手順とされているケースが多いようです。多肥、高温下でノキ勝ちの樹の場合は有効かも知れませんが、栄養成長ホルモンのジベの使用は、栄養成長が強まって二番花房の分化に悪影響を及ぼす恐れがあり、少肥が基本のSi22のファンの場合は草丈は適正で果梗枝も葉影の先まで伸びるので、ジベ不使用を伝えています。
一部で光合成の基本は炭酸ガスと水とお天道さんとお話ししましたが、私たちの活動が地球温暖化をもたらして、現在の空気中の炭酸ガスの平均濃度は400ppmを少し下回る程度まで増えています。イチゴが育つハウス内では、夜間の根や微生物、小動物の呼吸による早朝の900ppm位の高さから、光合成が盛んな頃の100ppm位まで上下しています。イチゴのDNAには400前後がちょうどよいはずですが、足りない時には補ってやることは必要です。光合成は葉緑体がお天道さんから「光子」を得て水を利用した明反応が始まり、気孔から得たCO2を使って「カルビン回路」と呼ばれる暗反応でグルコースを作りますが、注目すべきはカルビン回路にCO2を押し込む酵素で<ルビスコ>とあだ名される地球上で最も多く、葉っぱの半分を占めるたんぱく質です。このルビスコは酸素に対するCO2の比率が高いときほど良く働きます。逆に少ないときは酸素を押し込んで「光呼吸」という私たちの呼吸と似た作用を後押しして、イチゴの持つパワーを浪費させます。従ってCO2量が適当に多いほうがイチゴの生育は順調になります。もっともCO2が多くても温度が高過ぎると気孔は閉じますし、しっかり働く健康な気孔と根を作り維持するために、水、温度、湿度、肥料のチェックが第一なことは言うまでもありません。また燃焼式のCO2発生機を使用する場合は、不完全燃焼でCOが出ないようにメンテナンスをしっかり行いましょう。
定植から一番花房の開花までは最も手入れを要する時期です。苗も育苗場から移植されてストレスが掛かり、病害虫が出やすくなります。Si22の定期散布で一定の押え込みは可能ですが、もし発生した場合は初期の徹底した対策が肝心です。開花後は花にもハチにもクスリは好ましくありません。
イチゴは地温に敏感ですから、地温計で日々確認してください。出来れば北側、中央、南側と設置すればイチゴの生育と関係が見えてきます。13℃を切る日々が続くようだと矮化が心配になりますが、ボイラーでは地温は上がらないので、日照で上がった温度をなるべく下げないために、通路への廃ビニールの敷き込みを推奨しています。12月中旬~2月末までの間、2~3℃の上昇効果を得られるので、ボイラーの節約にも有効です。
根がしっかり張って樹の出来具合も良いときは、スソ玉まで成らす事はありかも知れませんが、樹は間違いなく疲れます。根がぐらつくようなら、摘花摘果で根の負担を軽くしてやるほうが二番の上りを遅らせません。二番が順調に上がることがイチゴづくりの要諦ともいえるので、樹の状態に合わせた成らせ方が大事です。
一番花が終わると追肥を入れる方が多いようですが、二番が遅れる一因になりかねません。ECが0.1~0.20あれば大丈夫です。新葉の色抜けが出て肥料が足りないようでしたら、出蕾を確認した後に化成肥料を少量やれば問題ありません。
展葉の具合、病害虫のチェック、クラウンの動き、マルチ下の白根でイチゴの健康状態が判断出来ます。具合が良くない時はまず古葉、タレ葉、果梗枝の除去をすれば1週ほどであらかた改善するはずで、肥料や資材の投入はその後の課題です。
3月になり気温の上昇とともにボイラー停止、サイド及び谷の開放、換気扇使用などで室温を20℃前後に調整します。灌水は厳寒期に比べ数倍が必要になります。多肥、高温の時は新葉が徒長しやすく、働き葉に被さって光合成を押し下げるので、Si22を数日葉面散布して葉面積を縮めて立性を高めるようにします。
春は芽数の増え方も盛んになり、あっという間に5~6芽ということも少なくありません。そうなると栄養は分散されて大きな果の収穫は望めません。元気のある3芽ほどを残して不要な芽を欠きます。日当たり、風抜け、栄養が改善されてイチゴの健全性は一段と向上します。葉欠きや芽欠きの後はすばやいかさぶた作りと病原菌の予防を兼ねてSi22を散布します。
サイドや谷を開放することで菌類や害虫の侵入は避けられません。少肥でSi22の定期処理をしていればリスクは低減しますが、病害虫を発見した時はその場での処理が大事です。ウドンコ病や灰カビ病などの表皮カビ系にはSi22の1000倍液、害虫にはマシン油の希釈液の散布で初期対応出来るので、台車やハウス内に常備しておきましょう。
炭ソ病、萎黄病、疫病などの立枯れ病
親株からの伝染による保菌株のハウスへの持込と、土壌中の病原菌による感染があります。親株からの伝染は二段階育苗で確実に無菌二次親株を作って採苗すれば、高い改善がみられますが、ランナーの出が良い品種でないと育苗が追いつきません。土壌中の菌は消毒になりますが、良い菌も殺すので良否の判断が難しいところで、台風などで雨風が荒れた後は病気が多発しやすいので要注意です。伝染性が強い病気なので苗場でも本圃でも怪しい株はいち早い処分か隔離を心掛けましょう。
怪しい株を改善したいときはSi22の100倍~200倍液を芯打ちしてみてください。病変が維管束まで達してなければ回復が期待できますが、数日おきに3回処理して新葉が展開しないのは発生源にしないためにも引き抜いて廃棄処分しましょう。
ウドンコ病、灰色カビ病、菌核病
発見したら患部を強めに処分します。周辺にも胞子が分散しているのでSi22の1000倍液を丁寧に数日散布します。効きが今一の時は500倍液にしてください。温度、湿度の条件や多肥が引き金になるので、見直すことも必要です。
輪班病
育苗期の降雨、高温で肥料切れの時発生が多くなります。株の枯死の心配はありませんが、成長不良になりやすいので、病葉を葉欠きしてSi22の1000倍液をまめに散布します。健全な新葉が出れば大丈夫ですが、追肥は入れ過ぎないように。
チップバーン、ガク枯れ
水不足、高温、チッソ過剰でカルシウム不足がチップバーンの因果ですが、ガク枯れは低温時に発現が増えます。カルシウムは大半の土壌では過剰気味ですが、カリウム、マグネシウムと拮抗して根から吸われにくいので、Si22を潅注することで改善がみられます。
トピック Si22は作物を健康にする
Si22の使用が作物の病気を改善に「時にはクスリよりも効く」と生産者さんが言われ、研究者さんは「何の病気にもなぜ?」と問われます。
農薬は基本的に病原菌や害虫を殺す毒で、その対象や使用作物、使用法は農薬取締法で定められていますが、有用菌や益虫にも毒であることは避けられません。従って安易に使うことなく、プラスとマイナスを勘案して採用を判断すべきです。シャーレや試験管での結果がハウスや圃場での再現は80%も出れば上出来で、半死半生で生き残った菌や害虫は次第に抵抗性を高めます。やがてどんどん厄介な状態に陥っていくことは、除草剤の失効や我々の抗生物質耐性菌の多発からも明らかです。全ての生物には子孫を残すというDNAが働き、かかるストレスが大きければ大きいほど抵抗性も強くなります。
ケイ酸はチタンと並んで最も水に溶けにくいため、植物に吸収されるには根酸や微生物酸で分解されるまで長い時間が必要ですが、Si22は溶融ろ過による製法で極めて小分子のため即効性があります。吸収されたケイ酸は細胞の間を流れる間質液に運ばれて細胞壁でナトリウム、ホウ素、カルシウムと協働して、細胞壁の強化、健全性の維持を図りますが、特に表皮細胞壁と気孔を作る孔辺細胞にはケイ酸の集積が認められて、その働きが注目されています。表皮細胞壁は我々の脳と神経の役割を担い、外部環境を察知して発芽、細胞分裂、伸長、分化、花芽形成、老化、器官離脱などの植物の一生の生理をコントロールします。気孔の孔辺細胞は葉の水分や体温の調節機能を図るとともに、CO2の取り込みを促進して光合成能力を向上させます。孔辺細胞へのケイ酸の集積は病原菌の侵入を阻止しているとの報告も見られます。(水耕栽培で銀塗布の制菌布とSi22の2000倍希釈液の比較試験では一桁上の制菌データを得ました)また細胞への病原菌の侵入という緊急時には、侵入菌を内から外へ押し出すドーム状のパピラ、輪っか状に取り囲んで菌の移動を制限するハローという抵抗性構造をケイ酸が中心になって作ることも解ってきました。ケイ酸は正常時は作物体の健康維持を縁の下の力持ちを演じ、緊急時には率先して現状の修復を行なう働きが認められます。ただ多過ぎる肥料にケイ酸が歯が立たないケースもまま見てきましたので、ご留意ください。
ハチ
イチゴの受粉には二ホンミツバチが最適と思いますが、近年ミツバチの数の減少や働きの低下が問題になっています。特にハチの最初の訪花をイチゴの花にさせないと他所へ行ってしまうとも言われています。マルハナバチの導入も増えていますが、花数に合ったマルハナバチの量を調整しないと、噛み過ぎにによる果形の乱れも指摘されるので注意が必要です。野バチや一時期ミツバチの天敵とされたアシナガバチも数を減らしているようで、原因はニコチノイド系農薬やハチに取り付くダニなどが一因とされていますが、本当のところはまだ明らかになっていません。イチゴ生産者さんとしては常にミツバチの動向や数、女王蜂の存在を確認して、異変を感じたらハチ屋さんと素早く対応することが求められます。
ダニ
この先一番やっかいな害虫になると予想されます。ダニの被害が目立つのはハウスサイドの閉め込みと保温の開始辺りからと、春のサイド開放頃になります。前者は育苗時に付いた苗からの持込が多く、後者は周辺に棲息するダニのサイドからの侵入が主になります。前者の対策は育苗中のチェックを怠らないことと、一番花開花までの徹底防除が大事です。後者は周辺環境よりハウス内がチッソ過多になっている場合は、ダニの害は避けにくくなりますが、適切な葉欠きや防除で低減出来ます。チリカブリダニなどの天敵防除はダニの密度と天敵の食欲のバランスを考慮した投入のタイミングが大切です。

不受青果(青花)
雌しべが黄色くならず成熟不良と思われる状態でハチが留まらず不受精果になり、頂果に多く発生するので経済損失が大きくなります。経験則からはリン酸とカリの過剰と感じていますが、詳しくは解りません。リンカリの使い過ぎが思い当たる方は、不使用にすることも改善の手立てになるかも知れません。
イチゴの栽培にはいろいろなコストがかかります。大きな方から施設代、機械代、暖房代、資材代、農薬代、電照代、肥料代などで、多忙を極めて雇用すれば人件費がかかります。必要だからと出費を顧みらなければ、作の後に手元に残るお金は期待できなくなります。厳寒期をまたぐ栽培ですからハウス施設は必須ですが、新規就農者に見られるいきなりの新設ハウス、高設栽培などの高額投資は無謀と思え、まずは空いたハウスの数年賃借でイチゴ栽培の技術を会得するほうが賢明です。次に高コストの機械でも不耕起栽培を取り入れれば、機械を使うのは数年に一度程度になり借用やリースでも間に合います。暖房代、農薬代、肥料代はSi22を使いこなして半分以下にした方も大勢います。まずは今かかっているコストを把握して、減らせる項目ややり方仕方を検討するほうが、コストを掛けてでも収量を上げようとするよりも確実にお金が残ると思います。雇用はともすれば一番のコストになりやすいので、生産規模や栽培計画をご自分の労力に合わせることが原点とも言えます。
イチゴは手の掛かり方も尋常ではありません。天気を別にすると、イチゴの出来は手入れで決まります。十分な手入れが可能な栽培面積は一人10アールとされるので、労力人数を掛けた面積を大きく超過することは、将来問題を抱える確率が高く好ましくありません。ただやり慣れた作業も、栽培暦と現実のギャップに目を向けて本当に必要なものと不要なものを見直して効率化を図ることも大切です。
知識とは海洋を航海するときの海図と羅針盤のようなものですから、多く待ち合わせるに越したことはありません。航海の途上、嵐や日照りや未知の生物との遭遇などが経験則を積み重ねることになります。イチゴ作りでもどちらの大事さも痛感する事が多いと思いますが、注意すべきは一方に偏った考えに固まらないことで、現場の体験を知識に照らし合わせて理解を深めることです。イチゴの花、果、葉、クラウン、根を見て生育の良否は経験が教えてくれます。お天道さん、水、温度、肥料、仕立て方が違えば生育も違うのが当然ですが、自分のイチゴはこれでよいと判断するには知識の裏付けが必要です。経験とは目視レベル、知識とは細胞レベル、顕微鏡レベルと考えたとき、同じイチゴがまったく違った姿に映りますが、100分の一、あるいは100倍にしたら同一と判断できる能力を養うことです。
Si22とSi25をご紹介し始めて16年が経ち、ご縁が出来た方は2000名を超しますが、今もって本当にファンと言える方は200名ほどでしょうか。その方々はSi22とSi25を使いこなされて、イチゴ作りに農作に役立っていると感じて頂いているようです。Si22とSi25を使いこなせた時、イチゴの果は10~20%重く、20~30%糖度が高く、日持ちが二日前後長持ちするようになります。葉は分厚く中型で、樹は立性が強く、根は本数長さともに50~100%増しになります。病気や害虫には従来に比べて数倍の厚さにもなる表皮細胞壁が抵抗性を高めて、相当減少するはずです。また葉裏の気孔の開閉機能が向上して、暑さ寒さに2~3℃強くなり、花粉粘性も高まって着果率も増加します。そして高い還元電位のために老化が遅くなり、樹が若さを維持して作期が長くなります。これらは研究成果や論文に裏付けられていますが、ぜひご自分の圃場でもテーマを決めて試験されてください。好結果を得るための絶対条件は肥料(特にチッソ、次いでリン、カリウム)を減らすことが第一です。チッソは葉が光合成で作った糖(グルコース)に加わることでたんぱく質、脂質、核酸を作る重要な元素で、イチゴの成長に欠かせませんが、多過ぎた時の弊害も半端ではありません。多過ぎるチッソは病害虫の狙うところとなり、葉に糖やデンプンとして溜まると光合成を阻害します。樹は徒長となり、葉影の増加、過湿環境、T/R率の崩れにより問題が絶えません。また土壌の酸性化の助長や菌叢のバランスを乱して成長不良の原因になります。リン、カリもその有効な働きは喧伝されますが、多すぎた時はチッソと同様にバランスを崩す原因になります。生物が成長して生きていくうえで栄養は必須ですが、腹八分でバランスの取れたものでなければならず、我々にも共通することはご理解いただけるでしょう。
「魔法のクスリはありません」
Si22とSi25は魔法のクスリではなく、土壌に唯一不足するケイ酸の肥料及び土壌改良材です。ケイ酸は分子量が大きいために、植物に吸われにくい、効きにくいとよく言われますが、Si22とSi25は肥料取締法の水溶性ケイ酸(wsi)の中でも溶融ろ過による生産法で極めて小分子のため、即効性に優れる資材と言えます。正しい使い方と正しい知識のもとにお使いいただければ「楽しいイチゴづくり」のお役に立ちます。
追記
一部で感性のことを言いましたが、日々のデータは勿論大切です。データに基いて感性を生かす訳ですが、データ収集には少なくとも温度計、湿度計、地温計、水分計は欲しいところです。出来れば北と南に設置すると、ハウスの状態がよく読み取れます。水分計を除くとほとんど1000円以下なので、すぐにでも揃えて、計測してみましょう。