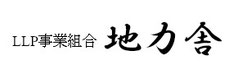よくあるご質問
Si25はゼオライトにSi22を含侵させていて穏やかな放出なので、問題ありません。液剤のSi22は強いアルカリ性かつ即効性なのでアルカリ資材との同時使用は、微量要素の吸収阻害を起こす可能性があり避けるほうが無難です。また強い酸性資材との混用は塩化作用を起こして石化し、どちらの効果も大きく低減するのでやめてください。肥料類は概ね中性なので同時使用は問題ありませんが、水溶性ケイ酸は肥効を高めるので少な目の肥料のほうが良い生育になります。本来、何の資材も単用がその効果が一番高く、混用されたときの効果についてのデータは大半のメーカーも知り得ないと思います。
日本土壌肥料学会はケイ酸を量障害と濃度障害のない唯一の物質としています。その裏返しはケイ酸はチタンと並んでもっとも水に溶けにくいためゆっくりとしか吸われず、障害がでにくいわけです。Si22とSi25は水溶性ですので量障害や濃度障害は意識すべきでしょうが、Si25の施容量は6kg/10aでその数倍くらいは問題ありません。Si22は100倍から500倍希釈では濃度障害の例はありませんが、作物によって強弱があるので小面積で試験の上お使いください。Si22を用量の20倍使った農業試験場からは弊害が出たとのことでしたが、常識外のデータです。
Si22とSi25は肥効を高めるので肥料の投与は1/2~1/5にや減らすほうが肥料やケイ酸の効果も現れやすくなり、コスト面からもお奨めです。肥料は有機でも化成でも土中の微生物の働きで、作物の根が好きな無機イオンに変わりイオン交換という作用で99.9%吸われます。残りの0.1%は細胞分裂中の根がヘモグロビンなどの分子量の小さな有機物を食作用、飲作用という形で直接細胞内にとりこみます。有機物の必要性は微生物のごはんとしてが第一で、微生物が正しい菌叢を作れていない圃場はいずれ地力がなくなるので、これまでの化成肥料の多用に見直しがなされています。
原液も希釈液も常温保管でかまいません。ただ厳寒期に凍らせてしまうと効果は半減しますので、特に東北、北海道の方はご注意ください。
Si22とSi25は水溶性ですがプラスイオンのカリウムやマグネシウムやカルシウムなどと結びついて流亡することは少ないと考えられます。したがってSi22やSi25を使用した圃場では吸われ残ったケイ酸が、そ年の後1~2年効果を維持するようです。さらに鉄やカルシウムと結びついているリン酸固定をはずして、リン酸の吸収率を高めるのでリン酸過剰圃場の改善に役立ちます。
Q.6 ケイ酸とカリの成分が似た他の液体ケイ酸とどう違う?
通常ケイ酸はケイ素と酸素が下図のように何万~何十万とつながった高分子です。

同じ液体であっても

が一つ(単量体)や(二量体)、三つ(三量体)のものが溶けている時と、何十万もつながっている分子が混ざっている場合では吸収される迄の時間が全く違います。
根や微生物が出す酸でゆっくりと吸われる大きさに分解されますが、環境によっては数か月~数年かかることも珍しく溶けて溶けてありません。溶けている物質が高分子のものをコロイド溶液と言いますが、真の水溶液(植物に吸収されやすい)かどうかは学校の理科で習うチンダル現象という方法で判断出来ます。ケイ酸が吸われて効果が出る迄の時間が全く違います。
あと大事な違いは一量体は+4のケイ素が-2の酸素を4つつかまえているので-4として、二量体は-3.5としてカチオン(+に帯電した物質)に働くことがケイ酸の効果ですが、何万もつながったコロイドでは+と-が互いに打ち消し合って電気的な反応は得られません。
Q.6でも述べたように、通常ケイ酸は

という単量体が酸素(O)を共有して何万何十万とつながって(シロキサン結合)、ヒモや面や立体の形になっています。ケイ酸は重なり合うと重合という形を取りガラス化して作物の葉を覆うと成長を妨げることがありますが、高分子のケイ酸で起こる現象です。Si22とSi25は単量体80%、二量体20%前後の構成のため、点で付着するので非常識な使用頻度、使用量でない限りご心配には及びません。
Q.3でもお答えしているように、Si22とSi25の使用は肥効を高めるので減肥が出来ます。低チッソで栽培すると病害虫も少なくなるので農薬コストも下ります。また、根量増加や気孔の性能向上により暑さ寒さへの抵抗性も増して、ハウス栽培には加温コストが低減出来ます。大半の圃場に残肥があるので数年無肥料、小農薬でも平均以上の収量を上げる方が多数おられます。数年すると地力が向上して減肥、減農薬、低コストの傾向は高まるはずです。一畝からでも始めてみることが充実した農業への第一歩になります。
ケイ酸は植物に吸収されにくい(水溶性ではないため)のですが、吸収されるとその主な働き場は細胞壁になります。細胞壁ではナトリウム、ホウ素、カルシウム、ケイ酸が働きますが、ケイ酸不足だとカルシウムの吸収も停滞します。(トマト尻腐れ病やイチゴのチップバーンが起き易くなる)ケイ酸とカルシウムが十分だと細胞壁は健全てのになり、動物の脳、神経、骨格としての働きを取り戻し、病害虫にも全身獲得抵抗性誘導(SAR)が起き、適切な対応がなされて、新葉、新梢が正しく成長するようになります。
土の中には50%程のケイ酸があるとされています。主体は石の粒に含まれますが、河川水や地下水からもたらのせるものや、植物体の循環によるものもあります。ところがダム、堰の増加や植物体の持出し、石粒子の劣化などで地下水を除いていずれも大幅に減少傾向にあり、ケイ酸不足を人的投与で補う必要があります。
Si22の葉面散布は葉の表皮細胞とクチクラ層を厚くして植物の健康維持と病害虫への抵抗性向上、徒長防止の効果が得られますので、潅水との併用が理想です。止むを得ず潅水のみの場合は回数や容量を2~3割増やす事でカバーすることをお奨めします。
Si22はケイ酸の単量体や小量体で通常マイナスの電荷を持ちますが、塩素やフッ素など電気陰性が強い物質にはプラスとしての働きをして、養分をバランスよく吸収させる働きが認められます。従ってケイ酸効果を得るためには植物の全成育ステージでの常用が望ましいのですが、週1回、10日に1回の施用であれば問題ないと思われます。人によってはSi22を15000倍程に希釈して水やりを兼ねている方も好結果を出されています。